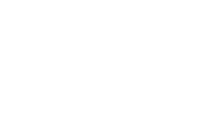タイルに惹かれるのは、
人類の記憶のせいかもしれない。
タイルを目にしたとき、なんとも言えない懐かしさや温もりを感じることはありませんか。もしかするとそれは、私たちのDNAに刻まれた遠い遠い記憶のせいなのかもしれません。というのもタイルの歴史は古く、紀元前2700年頃に建てられたとされるピラミッドの内部に飾られているのが確認されています。そんな昔のものが腐敗することなく現代にまで残っているのは、タイルが土を原料とするやきものだから。その耐久性や抗菌性はもちろん、自由なデザイン性から、タイルは現在も世界中で愛用されています。ここではタイルに関するエピソードをご紹介します。

京都 きんせ旅館

建築装飾としてつくられた陶磁器製タイルは、大陸から仏教がもたらされた時代から寺院などに用いられ、異国の色彩が描かれてきました。そして、幕末から明治時代に向かう中で日本人が出会ったのが、西洋建築における装飾タイル。当初は憧れの異国を象徴する存在であったタイルは、明治から大正、昭和へ、日本の意匠として進化を遂げていったのです。
京都の花街・島原にある「きんせ旅館」は、推定築年数250年の建物。もともとは「揚屋」という現在の料亭のような施設で、大正後期~昭和初期の時代に旅館となり、色とりどりのタイルやステンドグラスの設えが施されました。床面や壁面には、当時多くの建築家に愛好されたブランド「泰山タイル」が散りばめられ、独特な洋風の空間を形成していたのです。
かつてダンスホールとして使われていた空間は、現在ではカフェバーに。きんせ旅館を築いた曽祖母の代から受け継ぐオーナーが、当時の豪華絢爛な設えを活かし、現代の意匠として蘇らせました。時代を超えて、そこは全国のタイル愛好家、陶芸研究者の羨望の場所。アートのような美しさは、いまもなお新しい。